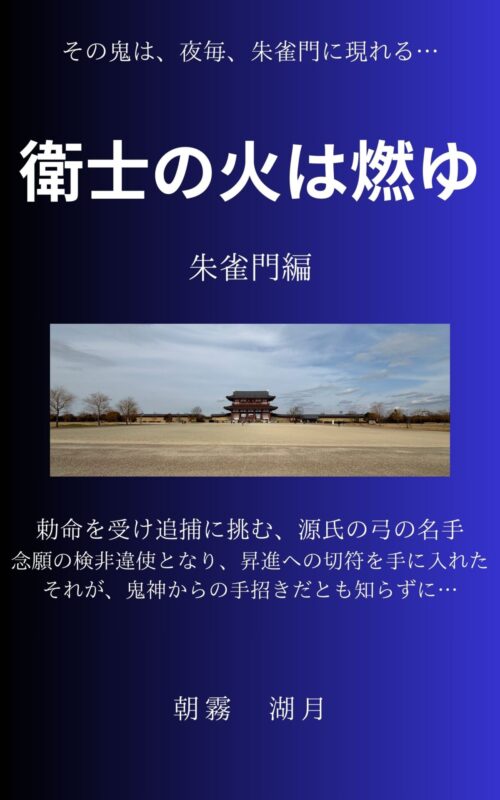『源氏物語』って長くて難しそうだけど、どんなお話?
ここでは、わかりやすく各帖にわけてあらすじをご案内しています。
『源氏物語』は54帖から成り「末摘花」はその6帖目のお話です。
「末摘花」の登場人物
源氏、頭中将、大輔命婦、末摘花、侍従、紫の上
「末摘花」のあらすじ
故常陸宮の姫君
亡き夕顔の面影が今でも忘れられない源氏の君は、いつぞや大輔命婦が耳に入れた故常陸宮の姫君に興味を覚えます。
常陸宮には生前から訪れる者も少なく、没後はさらに邸は荒れ果てていました。
そんな零落した宮家の姫に、思いもかけない素晴らしい人がいるかもしれないと、期待は高まります。
大輔命婦の母は源氏の乳母、父の兵部大輔は故常陸宮の縁者です。
姫君の実態を知る命婦は、源氏をあまり積極的に近づけたくありませんが、手引きを催促されて、琴(七絃の琴)をさわりだけ耳に入れるつもりで案内します。
物足りない源氏が姫君のいる寝殿へ近づくと、頭中将(義兄)に出くわします。
源氏の忍び先が気になり、宮中から後をつけてきたのです。
頭中将もこの姫君に文を送っていますが、一向に手ごたえがないので、お互い先を越されまいかと心がはやります。
紅花は懲り懲り
内気で人見知りの姫君に代わって、乳姉妹の侍従ばかりが応対していましたが、じれったくなった源氏は遂に逢瀬をとげます。
一言も発しない姫君に何となく異様な感じがして、後朝の文(逢瀬の翌朝男性から送られる文)もかろうじて、次の日の夕方に届けられます。
それからと言うもの、朱雀院への行幸の準備に追われたりと、長らく源氏は訪れませんでした。
雪が降る頃ようやく訪れ、雪明かりであらためて姫君の姿を見ると、あまりの醜い姿に言葉を失います。
中でも一番目をひくのが、鼻の先が赤いことでした。
唯一褒められるのは、末広がりの豊かな髪位です。
それでも源氏は、姫君だけでなく宮家のしきたりを守って窮状を生きる、年老いた侍女や門番にも憐れをさそわれ、その後なにかと物質的な援助はするのでした。
年の暮れに命婦が、姫君から贈られた正月の装束を届けます。
ひと昔前は、紅色は禁色として重んじられたからか、見事に紅色ばかりで揃えられていました。
源氏は命婦に、
なつかしき色ともなしに何にこのすゑつむ花を袖にふれけむ
(心ひかれる色ではないのに、どういうわけでこの末摘花に袖を触れてしまったのだろう)
末摘花は紅花の異名です。花に鼻をかけて皮肉ります。
以上より、「末摘花」と名付けられます。
赤い鼻に紅い装束…、二条院の紅梅を見てもうんざり気味の源氏は、美しく成長する若紫が、せめてもの癒しなのでした。